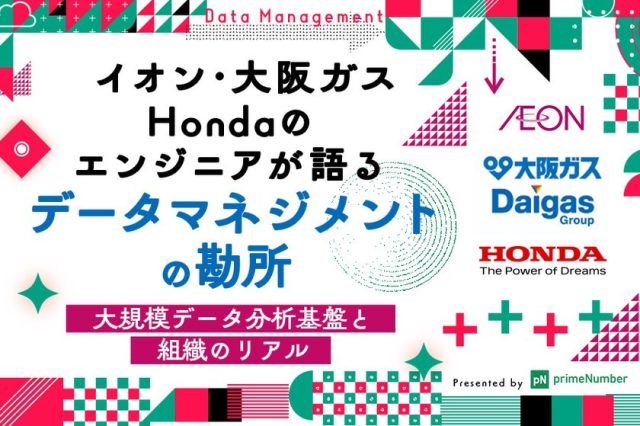本田技研工業株式会社(以下、Honda)SDV事業開発統括部でAD/ADASプラットフォームを開発する米森 力と、機械学習を用いたプロダクト開発のプロ、「ばんくし」こと、河合 俊典氏が語り合う。ソフトウェアデファインドビークル領域ならではの技術的難しさや⾯⽩さ。合わせてソフトウェア技術の活⽤余地、他業界エンジニアが活躍できる可能性などについて深掘りしてもらった。

この記事に登場する人
INDEX
自動運転とデータ設計。安全性×コスト×使い道のトレードオフ
——まずは、Hondaのモビリティ開発におけるデータの重要性を伺いたく、今関わられているお仕事の具体的な内容をご紹介いただきたいです。

私はHondaのAD/ADAS※部門で、先進安全機能開発に必要となる開発環境やデータ利活用業務に従事しています。自動ブレーキなどの事故削減機能や自動運転等の運転支援機能の開発で使われる基盤です。
先進安全機能はさまざまなソフトウェアとハードウェアの組み合わせで作られ、データ通信によって接続されています。事故削減機能や運転支援機能は人間の目や耳の代わりになるセンシングデバイスから入力された情報を人間の脳にあたるECUで処理し、人間の手足にあたるクルマのハンドルやアクセル等アクチュエータを制御することで、人間の運転を支援するようにクルマの動きを制御します。
この分野では、データが非常に重要であり、センシングデバイスの機能を高度化することで、より高機能な製品を作っていきたいと考えています。
例えば、車線変更などの動作を機械に代行させる際には、カメラやレーダーなどのセンシングデバイスをどこに配置するかが重要です。例えば、後方を見るためには、前方だけでなく斜めや右後ろ、後方を見ることができるよう配置します。
これらの情報を統合し、自車の置かれた環境や周辺状況、例えば変更先のレーン後方にクルマがいるかいないか等を分析することで、ハンドルを切るか否かを判断する等、ソフトウェアによる処理が行われておりカメラ、RADAR※、LiDAR※など、多様なセンシングデバイスから集められるデータをどれだけ適切に処理できるかが重要となります。
※AD/ADASとは 「⾃動運転(Autonomous Driving、AD)」と「先進運転⽀援システム(Advanced Driver Assistance Systems、ADAS)」の総称で、⾞両の運転をサポートし、あるいは⾃動で運転するための技術やシステムのこと。 ※RADARとは 電波を対象物に向けて発射し、その反射波を測定することにより、対象物までの距離や方向を測る装置のこと。 ※LiDARとは 近赤外線などの光を対象物に走査しながら照射し、その散乱や反射光を受光部でキャッチすることで、対象物までの距離や速度を計測したり、対象物の形状を特定することを可能にするセンサーのこと。

一番大変な処理ですね。

それに加えて、コストと価値のバランスを考慮することも求められます。デバイスはつければつけるほどクルマの値段が上がっちゃうんですよね。だから、やみくもにつければいいかっていうと、そうではなくて、必要な機能を実現する最小限の配置にするなど、意味のあるデバイス配置をきちんと考える必要があります。そして、配置したデバイスから取得するデータも、何をどうやって取得するかなど仮説を持って効果的に行うことが大切です。そのため、データの取捨選択や収集方法をデザインするのも私たちの仕事です。
データの多様性と量が魅力。ドライバーの意図をどう予測するか
——そもそも、米森さんが自動車会社でのデータ分析に興味をもったのは、どういう理由からですか。

まずは、データの多様性があるというところですね。カメラ、RADAR、LiDARなどデータ取得のためのデバイスも多様で、静止画、動画、GPSの数値、3Dのポイントデータなど多様な種類のデータが大量に取得できる。ドライバーが走行中にどのような操作をしているかもデータとして入ってくる。他にも、クルマの評判ということでは、SNSなどで交わされるレビューもデータの一つです。
そういった映像、テキスト、数値データ、構造データ、非構造データが入り混じる世界で、どうやってこれからのクルマを作っていくのか、そこに興味を覚えたんですよね。

Webサービスだと、1アクションに対してせいぜい1ログとか2ログぐらいですけど、クルマの場合は1秒間に入ってくるデータが多種多様で量もでかい。これをどう処理していくかは、コンピューターサイエンス的にも面白いし、機械学習的にも希少なケースですよね。


たしかに車の動きはデータでわかる。ただ、ドライバーがどんな意図で操作したのかは推測するしかないことも結構あります。でも、実は私たちが一番知りたいのはドライバーの意図なんですよ。

ユーザーの意図予測というのは、Webの世界でも一番難しいですからね。

わかりやすい例で言うと、飲酒運転かどうかを判断するとき。イメージとしては飲酒して運転をするとハンドルの切り方が雑になるとか、そういったところがポイントになりそうじゃないですか。
そこで、運転行動から飲酒の有無を推定することになるのですが、「普通の運転」と「普通ではない状態の運転」の違いっていうのを、データからどう見ていくか、これが結構難しいんですよね。
理想的かつ完璧な運転というのを、AIを使ってモデル化して、それとは異なる運転を異常値として判断し、AIモデルのように運転をアシストするというアプローチもあると思いますが、それでは今度は人間のほうが違和感を感じてしまうことがある。
以前、アメリカでロボットタクシーに乗ったことがあるんですが、ブレーキをかけるタイミングが自分のイメージと違いがあって違和感がありましたね。このような感覚が違っていると乗り心地があまりよくない(笑)。


海外のロボットタクシーは速度も遅いし、乗車時の不安度も大きい。珍しいもの見たさの、観光客しか乗っていないみたいな話も聞きます(笑)。こういった人間の感覚を考慮したとき、プロフェッショナルドライバーの走行をデータ化してAIを人間に寄せるか、ドライバーのほうがAIに寄せていくか、両方のアプローチを検討する必要がありそうですね。

ただ、普通に運転するのだったらそれでもいいんですが、クルマが走る環境は本当に様々あるので、全てプロフェッショナルドライバーが運転してデータを収集するというのは土台無理になってくるんです。

特に、日本の道路事情は複雑だっていいますからね。全ての道路が碁盤の目状に整備されていれば、いいんだけど(笑)。複雑であればあるほど、データ解析にあたってのドメイン知識が必要になると思いますし。
クルマだからこそ、データの扱いが難しい。そこが参入障壁にもなっているのかもしれないですね。Webプロダクトの世界でも、日本語の辞書の複雑さに音を上げて、撤退する海外のベンダーもありますから。
Hondaのデータ組織とクロスドメインの難しさ

それと、私がクルマでのデータ業務に関して興味をもったのは、センサーデバイスの配置やそのデータ収集の方法を考える人と、それらのデータを分析する人が、同じ部署にいること。米森さんも同時にその二つをやられているという点です。
Webの世界だとログ収集の設計をする人と、その統計処理や機械学習を使ったデータ分析をする人は、別の部署にいることが多い。例えば、フロントエンドのエンジニアがデータ収集部分を設計をして、ある程度データがたまったら、データ分析の部署を新設して機械学習を行うケースがわりと多いんですよ。それがデータ分析がうまくいかないことの理由にあげられることもある。
その点、Hondaさんではデータ収集と分析を同じ部署でやっていることが興味深いです。


そうですね。ただ、クルマの世界でも、データを先に集めて後で利用する方法を考えるという逆転現象は起こりえます。進化の速いドメインでは、特にそれが懸念されます。
例えば、データを活用するドメインが、二つに分かれている場合ですね。ADASは一つのドメインですが、これとは別にインフォテインメント※という別のドメインもある。一つのドメイン内でデータの整合性が取れていればよいけれど、複数のドメインで共通のデータを扱おうとすると、問題が出てくる。Hondaでも、ドメインをまたいだデータ活用はこれからの課題だと思います。
その点、テスラの「ドッグモード※」機能を知ったときは驚きました。ADASで使われるインキャビンカメラを使用して、車内にいる犬をモニタリングしたり、スマホを通じてエアコンをオンにして犬が社内で過ごせるようにします。ADASとインフォテインメントがクロスドメインでつながっているんですね。
クロスドメインでは異なる部署がそれぞれのドメインを越えた活動をして、相互に連携する必要がある。Hondaも今、チャレンジしているところです。
※ドッグモードとは
テスラの技術で、ペットを車内で待たせている間も車内を過ごしやすい温度に保つこともできる機能のこと。
※インフォテインメントとは 「IVI(in-vehicle infotainment)」。主に⾃動⾞(⾞載システム)について⽤いられ、「情報の提供」と「娯楽の提供」を実現するシステムの総称、あるいは特に情報‧娯楽の両要素の提供を実現する(⼀体化された)システムの呼び名のこと。

そういうクロスドメインの取り組みの具体例を教えていただけますか。

実は、Hondaはもともとそういうのが好きだったりするんですよね。だから、部署を越えて一緒にアイデアを出すということはよくやっています。ただ、それを実際のクルマに落とし込んだときに、どういうスキームでやるのかははっきり決まっているわけではありません。
ここにはもう一つ課題があって、データ分析ってやはり難しい専門スキルで、全員がデータ分析できるわけじゃない。データ活用のアイデアを豊富に持っている人とデータ分析をやる人が同一人物であれば理想的ですが、現状では必ずしもそうではありません。この両者が上手に連携しながらアイデアを実現するという動きができてくると、SDV開発はより加速すると思います。
理想のデータドリブン組織とは。期待値のすり合わせが重要

——今のお話ですが、データ活用を考える人とデータを分析する人が別々の場合、双方のコミュニケーションを密にとらなくてはいけませんね。どんな工夫をされていますか。

まず、Hondaの組織全体でいくとデータアナリティクスを専門にやっていく横断部署があって、そこで全社のデータ利活用に対して、データ分析コンサルティングを行っています。
ここで問題になるのはやはりコミュニケーション、言葉の違いです。分析を支援する側、支援される側での言葉の違いもあるし、Hondaならではの専門用語、ドメインならではの専門用語もあるから、外から入ってきた人は最初は分かりづらい。
同じ自動車メーカーでも言葉が違いますからね。みんながADASの専門用語を知っているわけではないので、コミュニケーションに結構苦労するところはあります。でも、今は実際のデータ分析プロジェクトを一緒にやることで、そこを乗り越えて、オープンに共通言語で話せるようになってきている。そこが、Hondaの強みにもなってきていると思います。

言葉の共通理解もあるけど、サービスに関するお互いの期待値のすりあわせも重要ですよね。例えば、クラウドのサービスだと、ダウンタイムは最低このぐらいという数字の目安があるけど、なかなかデータ分析ではそういう期待値合わせって難しいのではないですか。


できるだけ期待値が合うようにする工夫をしています。例えば、データ分析の要望をいただいた後、まずはヒアリングをして、基礎集計をして、分析デザインをして、作った企画をもとにしてユーザーとの期待値を合わせる。そこで期待値が合ったら実際の分析業務に入っていって、最後にレポーティングする。そういう一連のフローを見える化しつつ、分析の過程が今どこにあるのかも情報共有ツールを使って、依頼した側も「今こういうことやっているんだな」というのがわかるようにしています。

そのあたりは、確かにクルマならではの「堅牢なものづくり」という感じはしますね。データ分析では、お互いの期待値のすり合わせができていないと、結局、よくわからないものができてしまう。
Hondaさんの場合、アウトプットはクルマですから、そういうハードのレベルになってくると、一個一個の損失とかコストリスクが大きいですからね。そこに対する意識の高さは、Hondaさんならではだと思います。

そこは、私が今まで歩んできたキャリアの経験、失敗があるからこそ、できているのだと思います。私はかつて大手SIerでデータ分析コンサルティングをやっていました。そこのお客様は社内ではなく、実データをもつ外部の企業で、社内と社外の明確な壁がありました。だからこそ、コミュニケーションを密にして、期待値をすり合わせなければいけませんでした。「何をやりたいのですか?」「これでいいですか?」という確認をしてからデータ分析を始める。その結果、お客様の期待と違えば、どこが違うのかを一緒に考える。Hondaに来てからもそういうプロセスが必要だと思って、その役割を自分で担うようにしました。
それと、この期待値合わせが不可欠な理由はもう一つあって、それは社内でデータ分析のスキルを持っている人を確保するのが難しいということなんです。
そういった数少ない人たちがより効果的に非ソフトウェアエンジニア、クルマのエンジニアの人たちとしっかり連携していくためには、ゴールとそれに向けてお互いに折り合いをつけるべきところは何なのか、期待値を合わせることが欠かせないんです。
ルールベースの開発とAIベースの開発。ブラックボックスの壁
——Webとモビリティ、データ収集の違いと併せて、データ分析にあたって共通する課題も出てきました。WebでもSDVでも、アイデアと一体になったデータ分析、ドメインを越えたデータ活用とソフトウェア開発がシームレスにつながれば、それは魅力ですね。

もちろん、Hondaもドメインを超えたデータ分析・活用の連携をやっていきたいと思っています。なぜなら、ADAS領域での国際競争は激しく、それに打ち勝つためには、これまでのやり方をガラッと変えないといけないからです。
これまで、日本はクルマの技術で世界をリードしてきましたが、やはり電気自動車の台頭による変化はすごく大きい。日本のこれまでのものづくりのやり方がうまくソフトウェア開発にも活かせればいいんですが、そのままでは難しい。
例えば、車両制御のソフトウェアも、これまではルールベースでいろいろ作り上げてきましたが、今はデータを中心としたAIベースにシフトしてきていて、開発のやり方自体を変えていくことが求められてきています。
Hondaは昔から制御ロジックの品質確保に、かなりの時間や労力をかけてきました。構築したソフトウェアをテスト車両に搭載し、公道を走行させて、データを取って品質を担保してきました。しかし、これからは車両制御のソフトウェアもデータドリブンでモデルが構築されます。いわば、これまでホワイトボックスだった世界からブラックボックスの世界に移行しているわけです。


ブラックボックスのソフトウェアのテストは、「テスト対象の入出力が期待通りで、外側から見た実績として問題ないから大丈夫というアプローチです」と言い切ってしまう。これまで安全性を内部ロジックを元に論証してきた日本の自動車メーカーには馴染みのないものです。「想定されるシナリオに対して、網羅的にシミュレーションテストをやりました」と言っても、「本当にそれで大丈夫なのか?」と必ず言われる。それに対して、「シナリオの網羅性とシミュレーションの結果としてはこうなっています」と言っても、「中身としてどうなんだ?」と問われると、AIが出した答えの裏側にあるロジックや理由はブラックボックスだから答えようがないんですね。
それは、実はデータ分析の効果を説明するときにも同じ問題があるような気がします。データ分析はトラディショナルな方法だと回帰分析などの手法を使えば、ロジックはクリアできたというところがあったんです。しかし、ニューラルネットワークベースのデータ分析が入ってくると、中身がどうなっているのかがわかりづらくなってきている。私はトラディショナルなデータ分析手法で生きてきた人間なので、そこは結構気持ち悪いところがあります。
気持ち悪いっていうのは、ニューラルネットでやったほうが、予測精度や認識精度では、トラディショナルな方法を上回ることがあるからです。もちろん、従来とは比べものにならないほどデータをたくさん使った上での結果なんですが、高い精度が出たとしても、なぜ「高いのか」をクリアに説明できない。このような説明可能性の問題は、ブラックボックスで作られたソフトウェア品質を判断するときに孕んでいる問題と似ているなと感じることがあります。

人間って意外と統計モデルの考え方に弱いところがありますよね。世の中のことはだいたい統計的に起こってるわけですが、一つでも悪いことがあると、すっかり落ち込んでしまう(笑)。
身近なことを短いスパンで考えるのではなく、もっと大きく統計的に考えれば、納得するわけだけれど、それを理解するのが大変。でも、それが人間の性質だとすると、機械学習の成果を説明するのはけっこう大変なことだと、私も最近思うようになりました。


説明が難しいというのは、説明する相手、お客様がどのような人たちであるかによっても、変わってきますね。

私が所属するエムスリーでは、医療関係者向けのサービスやプラットフォーム構築をやっています。つまり、お客様はお医者さん。そこには論文を読んで知見を豊かにするというカルチャーがある。職業柄、みなさんは勉強熱心で、実験結果の統計処理にも慣れている。だから、「確率はこうです」という伝え方にも納得してもらえるのだけど、そこがクルマのユーザーとは違うところなのかな。

たしかにお医者さんを相手にするのと、これまでずっとクルマの品質管理をしてきた文化の人と話すのとでは、ちょっとギャップがあると思います。

結局は、データサイエンスにおけるAI活用という、きわめてイノベーティブな技術革新も、昔からのデータの利用者との対話の積み重ねがないと、その良さが浸透していかない。その両輪が必要なんですね。
シミュレーション化する自動車開発とその課題

ところで、以前からシミュレーター関連の研究ってあるじゃないですか。シミュレーター上で何かを提供して、実際動かすのは別の人という話って、クルマではあまり現実的ではないんですか。

自動車開発にシミュレーションを取り入れることは、結構積極的にやってきてますし、これからより拡大することだと思っています。キーワードで言えば、デジタルツインですかね。
もともとクルマの品質を検証することを考えたときに、いろんなやり方があると思うんですけど、一番シンプルなのは作ったものを車に乗せて走らせて確認するという作業です。でも、毎回それをやるのは手間とコストがかかります。
だから、テスト自体を仮想のシミュレーターに置き換えてやるというのはリーズナブルだし、それはやってきています。
ソフトウェアシミュレーションや、ハードウェアを使ったシミュレーションもあったりと、さまざまなやり方があります。

すごいですね。いろいろ試せるんですね。


ロジック的にはそうです。ただ、やはりこのシミュレーションでも、シミュレーションの結果が実際とどのくらい一致するのかというバックテストが結構大事になってきていて、品質の説明をするときにはこれが不可欠になります。
できれば、ソフトウェアシミュレーションよりハードウェアシミュレーションでやったほうがよりリアルに近いし、信頼性も担保できるし、説明もしやすいんですが、ハードはやはりコストがかかるし、組み合わせの検証はさらに難しいです。それで、実務上は様々な検証条件に応じて使い分けているんです。
もちろん、自動車業界全体の流れは、クルマのハードのテストで品質を保証するというのが中心だったやり方から、シミュレーションを活用するようにシフトしてきています。より広く捉えれば、開発環境自体がリアルな世界からバーチャルに変わる。つまり、コンピューターを使ったリソースをしっかり確保するというふうにシフトしてきてるんですよね。
中国やアメリカのEV開発が強いのは、そういう考え方が最初からネイティブに備わっているというところです。コンピューティングリソースあるいはストレージに対する投資も、そこから来ているんです。トップ層もハードウェアエンジニアではなく、ソフトウェアエンジニア出身ですからね。
世の中は間違いなくAIシフト、シミュレーションシフトに進んできてるわけで、Hondaもトップ層がそのような現状を把握し、変わっていかなきゃいけないと思います。例えば、ばんくしさんが僕の上司だとしたら、説明がすごく楽になるだろうなって(笑)

自動運転は“ルール”だけでは動かない。だからこそ、チャレンジのしがいがある
——ここまで、さまざまなお話を伺ってきましたが、実際のクルマ開発では、複雑な現実の道路環境にどう対応しているのか気になります。ルールだけでは割り切れない場面も多いですよね?

そうですね。私たちは走行シーンにおける四輪以外の二輪や自転車や歩行者なども含めて「交通参加者」と呼んでいます。
Hondaが「LEGEND」に自動運転レベル3の機能を搭載したとき、自動運転のODD(運行設計領域)では高速道路での走行を前提にしていました。高速道路には自転車や歩行者は入って来ないという前提です。このときはルールベースで実現することができました。
しかし、一般道の走行を前提にすると、交通参加者は多様で人もいるし、自転車もいる。掛け算でパターンやデータが増えていくわけです。これはもはやルールベースでは無理で、パターンを学習するアプローチに変える必要が出てきています。

これからは、ルールベースでやるところと、複雑なモデルを統計的に解析して何とかするところと組み合わせの世界観になってくるのかな、という気がしますよね。

我々としても、やはりそういったルールベースで安全なクルマを作ってきた実績があります。そういう今までHondaが大切にしてきたところは大事にしつつも、一方でそれだけでカバーできない領域というのはデータでどう補っていくのかをしっかり考えたいな、というふうには思うんですけどね。
ちょっと前まではコンポーネントごとにAIを導入していました。例えば、クルマの外界認識のコンポーネントとクルマを制御するコンポーネントに分けて、それぞれAIで作り、それらをつなげて全体を実現するという方法でした。
最近はEnd-to-End、外から入ってきたセンサー自体が大きなブラックボックスのAIに入っていて、直接クルマを制御するという流れになっています。ルールベースでやっていくところと、データでやっていくところの割合について、どれがベストミックスかをいろいろ考えているところです。

なぜ、Hondaは3ヶ月でデータ分析プロジェクトを回せるのか
——データ分析のプロジェクトについて、それを回すスピードのお話もぜひお伺いさせてください。

一般的にはだいたい3ヶ月ぐらいで一回転するプロジェクトが多いと思います。社内で分析部隊を持つところの良さは、そのスピード感と思います。私がSIerにいたときは1年間で2案件とかでしたから、今のほうが回転は圧倒的に速いですね。
そこは内製の強み、外部を使わない分だけ、データのやりとりや契約事務などのオーバーヘッドがないですから。プロジェクトのスピードは重要で、たくさん経験することで、メンバーも成長するし、スキルも上がる。これは他の仕事でも同様にいえることです。

今は学術論文に書かれていることをいかに早く社会実装できるかが勝負みたいなところがありますから、そのスピード感はたしかに重要ですね。

著名な学会での発表が、今は1年後、2年後には実際使われるレベルで試されているということがある。アカデミックな世界と実世界との距離がすごく近くなっているんですね。

いろんなものが短いスパンでできるようになりましたよね。Hondaさんもそれに適応してデータ分析のところを圧縮し、3ヶ月で1プロジェクトが終わっている。例えば、AIの世界でも、Hondaさんと同じように期間を縮めていかないと、負けちゃいますよね。

そうですね。やはり私は新しいことをやりたくて、Hondaに入ったわけで、当初はデータ分析組織を作ったり、データ人材採用といったところまで担うことができるとは思っていなかったんです。
Hondaは新しい物好きの人が多いので、データに関しても意外とやれることは多かった。クルマの歴史を見ても「日本初」「世界初」の技術をつくることは会社文化としてあるので、新しい取り組みは奨励されているし、やりやすい部分もあると思います。

Hondaさんはクルマの世界で日本のイノベーションを生んできた会社ですからね。

本田宗一郎という創業者が偉大すぎて、大変ですけど(笑)、創業者が創ってきたイノベーションの風土はいまも強くある。私たちもそのチャレンジ精神を受け継いで、SDVの時代を切り開いていきたいと思っています。

※掲載内容は2025年7月時点のものです