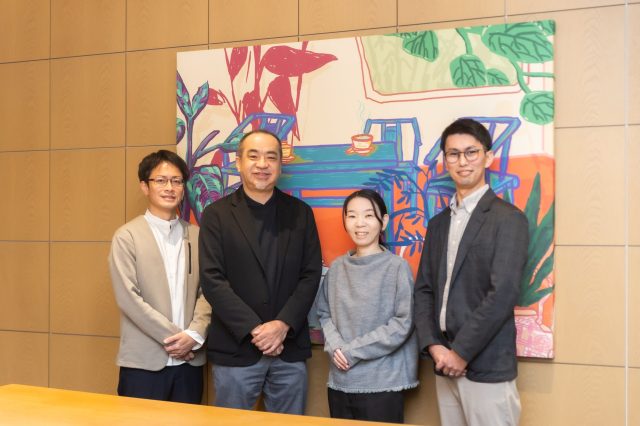JR博多駅から徒歩7分。シェアオフィスの8階に2024年3月に入居したのは、本田技研工業(以下、Honda)の長い歴史でも初めての福岡のソフトウェア開発拠点「Honda Software Studio Fukuoka」だ。Hondaの福岡拠点開設の狙いを、SDV開発にあたっての全国拠点戦略とともに紹介する。
博多で育むSDV開発。Hondaの地方拠点戦略と福岡拠点「Honda Software Studio Fukuoka」

この記事に登場する人
INDEX
優秀なソフトウェア人材を求めて、栃木から全国へ
——「Software Studio」という名称は、 HondaがSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)開発領域を深化させるべく、これまで栃木のBEV開発センターに集中していた機能を全国に分散しているソフトウェア開発拠点の総称ですね。
すでに、東京・品川(天王洲)のほか、大宮、大阪、名古屋にあり、福岡拠点はそれらに続くものです。なぜ、新たな開発拠点を全国に展開する必要があるのか。その狙いを廣中さんに伺わせてください。

Hondaに限らず、いま世界の自動車業界はソフトウェアを基軸にモビリティの中と外を繋ぎ、機能を更新し続けることで、ユーザーに新たな価値および体験を提供し続けるためのプラットフォームづくりを急いでいます。
私たちはもともとそのSDV開発を栃木のBEV開発センターで行っていました。しかし、SDV戦略が重要になるにつれて、優秀なソフトウェア人材を全国からもっと集める必要がでてきました。ただ、栃木は人材獲得という点では地理的に不利な面があります。それなら、私たちが率先して栃木を飛び出し、全国に複数の開発拠点を設置し、各地域のエンジニアと仕事をすることが大切だと考えるようになったのです。

——各拠点の立地の特徴やネットワーク環境などインフラはいかがですか。

Software Studioの各拠点は、いずれもターミナル駅から数分の距離に位置するオフィスビル内にあります。大阪拠点は500人規模、名古屋拠点は250人規模、福岡拠点は50人規模などスペースは異なりますが、スペースの上限は特に定めておらず、キャパシティが不足すればオフィスの移転も考えるなど自由度は高くしています。
また、PCやネットワーク環境などの各拠点の開発インフラは可能な限り高いレベルで統一するようにしています。実機を模した開発用シミュレーターHILS※をオフィス立ち上げ当初より導入しているオフィスもあります。
※HILSとは HILSは、Hardware In the Loop Simulatorの略で、ECUのテスト装置のこと。
——SDV開発を機能ごとに分担して、それを全国で完全分業的に担当しているのでしょうか。

いえ、一つの拠点が単一の領域だけを専任で開発するという形ではなく、SDV開発で必要な領域、例えば、EEA(電子プラットフォーム)領域、IVI(インフォテインメントシステム)領域、ASI(AD/ADAS)領域、ELS(充電系データ分析)領域などを、各々の拠点をまたいで分散一体開発を行っています。
福岡の人の地元愛はそのままに、Hondaの新拠点で仕事を
——地域ごとに地元の産業の特徴がありますね。それも意識されていますか。

例えば、国内における自動車産業集積地の一つである名古屋に進出した背景には、車載領域のソフトウェア人材を獲得する点で有利という判断がありました。
福岡は九州の産業中心地なので、九州全域から優秀な人材が集まるという立地的な魅力があります。しかも、福岡の人は地元愛が強く、関東/関西からUターンする人も多いのです。
福岡は、必ずしも車載領域のソフトウェア人材は豊富ではないけれど、大手IT企業の支店やスタートアップが多く、産業用ロボットやデジタル地図の開発に関わるエンジニアもたくさんいます。そういったエンジニアたちにHondaのSDV開発の魅力を伝える上でも、福岡に進出することには大きな意義がありました。

——IT・Web業界では、いまやオフィスに縛られず、在宅やリモートでも十分に対応できる開発領域が増えていますが、なぜHondaはオフィスにこだわるのでしょうか。

車載ソフトウェアの特徴とも言えることですが、クルマに搭載される部品点数は数多く、開発する機能も極めて多いため、それぞれが協調しながら開発していかないと失敗してしまいます。自動車のソフトウェア開発は現状ではすり合わせが必須なんです。そのため、Face-to-faceのコミュニケーションが必要だと考えています。
また、Hondaではワイガヤ※の文化があり、ワイワイガヤガヤ言いながら、他の人の領域にも首を突っ込みたがる従業員がたくさんいます。そういった文化を大切にしたいという理由から、オフィスでの協働にこだわっています。
※ワイガヤとは 「ワイガヤ」とは、「夢」や「仕事のあるべき姿」などについて、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論するHonda独自の文化のこと。
今はまだ小所帯。しかし、お互いの顔がよく見える
——全国展開の理由や狙いがわかったところで、今度は福岡拠点長の宮地さんへ福岡拠点ではどのような開発をしているのかを伺います。現時点(取材時:2025年6月)で、「Honda Software Studio Fukuoka」に在籍するエンジニアは何名ですか。

電子プラットフォーム開発部が3名、スマートキャビン開発部が2名。先進安全・知能化ソリューション開発部が1名ですね。彼らの前職をたどれば、エンジンECUの組み込みソフトを開発していた人もいれば、Androidアプリの開発をしていた人もいます。
まだまだ小所帯だからこそ、お互いに顔の見える関係があると思っています。栃木だと大所帯なので、どうしても縦の関係が軸になってしまいます。その点、福岡では横並びで、お互いにどのような仕事をしているかがわかるし、コミュニケーションもとりやすいんです。

——福岡拠点の開発ミッションはどのようなものでしょうか。

次世代モビリティ社会において、クルマの新たな価値を創造するE&Eアーキテクチャ※とソフトウェアプラットフォームの開発がミッションの一つです。具体的には、セントラルECU、テレマティクスECU、自動運転ECU等のアーキテクチャ構成ECUの制御システム開発やソフトウェアプラットフォームの開発を進めています。
同時に、AD/ADAS※システムに必要な次世代地図システム開発も担当しています。
※E&Eアーキテクチャとは クルマに搭載されたECU(電子制御ユニット)やセンサー、アクチュエータなどを繋ぐシステム構造のこと。 ※AD/ADASとは 「⾃動運転(Autonomous Driving、AD)」と「先進運転⽀援システム(Advanced Driver Assistance Systems、ADAS)」の総称で、⾞両の運転をサポートし、あるいは⾃動で運転するための技術やシステムのこと。
非自動車のソフトウェアエンジニアに、SDV開発の課題と魅力を伝える
——宮地さんは、2024年に地域拠点開発の先遣隊として、30年以上勤務した栃木拠点から福岡に単身赴任してきたと伺っています。最初は人材集めに苦労されたんじゃないでしょうか。

赴任して、すぐにエージェントを通しての人材募集活動や採用イベントを進めました。「福岡は若い人の人口伸び率が全国でも高い街。人材は豊富だろう」と考えていましたが、最初は正直、苦戦しました。
特に大変だったのが、IT系人材への訴求ですね。自分の持っているスキルとクルマで必要なスキル、これをどうやってうまくマッチさせていけばいいのか、イメージがわかないという声が多かった。
それに対しては、「これからのクルマはスマホのようになる。モビリティの中と外が繋がり、機能やOSの更新情報を取り込みながらたえずアップデートし、進化を続ける。そこは、ITシステムやスマホアプリの開発とよく似ている」と、SDV開発の魅力を語り続けました。

——自動車開発における厳しい品質基準や安全性担保についても、非自動車業界のソフトウェアエンジニアはピンとこないという話もよく聞きます。ミッションクリティカルの度合いが違う、と。

クルマにおける走る・曲がる・止まる技術はきわめて重要です。Hondaでは、2050年に「交通事故死者ゼロの実現」を目標に掲げており、事故を未然に防ぐうえでも、ソフトウェア技術の活用がますます重要になっています。自動車開発では、ソフトウェア品質が鍵になるという話はきちんと伝えていきたいですね。
それと同時に、SDVの世界ではソフトウェア品質に対する考え方の切り分けも重要になると考えています。エンジン制御など安全に直結するミッションクリティカルなレイヤーでは、安全性の検証に時間がかかります。たった一つのバグでも致命的なリスクになりうるからです。
一方で、安全にはダイレクトに影響しないインフォテインメントなどの領域では、堅牢なシステムであること以上に、新規機能の追加やソフトウェアアップデートのスピードが求められます。ミッションクリティカルな領域とそうではない領域とでレイヤーを分けながら、多様化したソフトウェア開発の考え方やプロセスが必要になってきています。
スピーディーな開発が求められる領域では、IT領域からキャリア採用で入ってくる方々から私たちの方が、ソフトウェア開発の考え方やプロセスを教わることのほうが多いかもしれません。安全・品質の文化はこれからも守っていきますが、これからHondaに転職していただける方々には、IT・Web業界の文化をHondaに持ち込んでもらえることも期待しています。
サプライヤーでは得られなかったクルマ開発の深さと広さを実感
——椛さんは、福岡拠点のキャリア採用第一号として2025年1月に入社されました。どういう経緯だったのでしょうか。

私は福岡県柳川市出身で、大牟田市にある有明高専卒という根っからの福岡県人です。前職では、福岡市博多区にオフィスがある自動車部品サプライヤーのグループ会社でエンジンECUのソフトウェア開発をしていました。17年働いた前職を辞め、転職しようと思った最大の動機は、ひとつの会社に勤め続けるのも悪くないけど、一度きりの人生だし新しい仕事にチャレンジしてみたいと思ったからですね。
実は以前、Hondaグループである本田技術研究所の電動垂直離着陸機「eVTOL」開発の募集に応募したことがあったんです。クルマとeVTOL、モビリティという点では同じですが、畑違いの仕事。それでもワクワクするような新しい仕事に無性に挑戦したくなったんです。
結果としては最終的に不採用となりましたが、面接を通してHondaという会社はすごく魅力的だなと強く印象に残りました。

——その時は採用に至らなかったんですね。

はい。ある日、登録していた転職サイトにHondaから「福岡拠点での四輪電子プラットフォーム研究開発」という募集内容で直接採用オファーがありました。Hondaの工場も近くにないのに、なぜ?と一瞬思いましたが、Hondaの名前を見て、再び転職活動にチャレンジしたくなりました。
それで書類を送って面接を受けて、現在に至るというわけです。
——現在は、どんな仕事をされていますか。

入社後、2ヶ月のSDV研修を受けたあと、現在は、2026年に量産開始される製品のCoreECU※開発に従事しています。その中で、私は製作所やサービス(ディーラ/整備修理工場)で使用される故障診断ツールにCoreECUから診断結果を応答する「診断機機能」を担当しています。
栃木に開発チームがあり、私はそこに福岡から参加しています。現在、月の半分は栃木に出張しています。
※CoreECUとは クルマにおける電子制御ユニット(ECU)の中でも、特に重要な役割を担う中枢的なECUのこと。
——出張は苦ではないですか。

採用面接のとき「栃木拠点との協業なので、頻繁に出張がある」と聞いて少々不安になったことはたしかです。地図を見ると、むちゃくちゃ遠いじゃないですか(笑) でも、何度も行き来するうちに慣れてきました。
栃木に行けば、設計室の階下に実際のクルマが何十台もあって、そこに自分が開発したソフトウェアを組み込んで、実際にクルマを動かしながらデバッグができます。前職のサプライヤーのときは、自分がクルマのどの部分を開発しているのか、実感が沸かないことがあったのですが、Hondaではそういうことはないです。
福岡に根づく、「人間尊重」のHondaフィロソフィー
——Honda入社、6ヶ月あまりですが、職場の雰囲気はいかがですか。

Hondaのエンジニアは一人一人の能力がめちゃくちゃ高い。それはSDV事業開発統括部に中途で入ってきた同期にも同じことを思います。ただ、Hondaは自分からやり始めないと、誰かが手取り足取り教えてくれる文化ではないんですね。PCのアクセス権の設定さえも、自分でやらなくちゃいけなかったんです(笑)
でも、最初のSDV研修で各拠点にキャリア入社した同期の仲間と交流ができました。Honda文化に慣れていく上で、それは心強いものがありました。また、自分もこれまでクルマの世界にいたとはいえ、Hondaに来てあらためてその世界の広がりを実感しています。自分が挑戦すべき課題が、ぐんと広がった感じです。

一人ひとりが自ら動かないと何も始まらないのは、よくも悪くもHondaの文化といえるかもしれません。
完全分業で他の人の仕事が分からないというのではなく、お互いがお互いの領域を越境しあうのもHondaの特徴。だから、一人ひとりの仕事量は増える。でも、抱えすぎるとつぶれてしまう。
だからこそ、Hondaのエンジニアはよく喋るんです。手を動かしながら、コミュニケーションをとって、お互いをカバーしあう。

たしかにコミュニケーションが活発で、しかも、みんないい人たちで、お互いの仕事をカバーし合っていますね。そういう風土や文化が、「仕事は忙しいが、仕事はやりやすい」につながっていると思います。

自立・平等・信頼という3つの要素をベースにした「人間尊重※」のHondaフィロソフィーは、福岡拠点にもしっかり根づかせたいと思っています。
※人間尊重とは Hondaフィロソフィーの基本理念。「自立」「平等」「信頼」の3要素をもとに、お互いの個性を尊重し、お互いに平等なパートナーとして信頼するという、Hondaが大切にしている考え方のこと。
——最後に、「Honda Software Studio Fukuoka」としては、今後、採用にあたってどんなところに力を入れていきたいですか。

博多に集結するITスタートアップとの出会いを求めて、交流会などのイベントにも積極的に参加し、Hondaでソフトウェア開発をする魅力をアピールしていく予定です。
現在、私たちが入居するシェアオフィス「SPACES博多駅前」でも、企業の枠を超えたエンジニア交流会などが開かれているので、そこに廣中・宮地両名の名刺を貼り付けたチラシを配布したりしているんですよ。将来的には新卒採用も視野に入れているので、北九州地区の大学との産学共同研究にも関心があります。
——Hondaの新たな息吹が、福岡からも感じられますね。ありがとうございました。

※掲載内容は、2025年9月時点のものです。