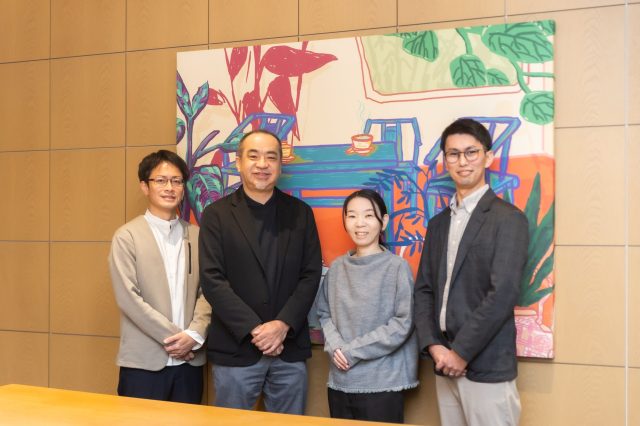HondaのSDV事業開発統括部で戦略・企画立案やプラットフォーム構築など“上流工程”に携わる企画セクション。これまで栃木と東京に分散していた機能を、2025年4月に東京・赤坂オフィスに集約。Hondaが思い描くSDV実現のために、戦略・企画・開発・運用・保守のプロセスを一気通貫で管理する体制が生まれている。ふだんから協働している各部長たちが改めて一堂に会し、企画という仕事と相互の連携、これから採用したい人材などについて語り合った。
SDV戦略・事業企画を上流工程から一気通貫・爆速で推進するために、Hondaは何をしているのか

この記事に登場する人
INDEX
SDV事業開発統括部における戦略・事業企画とはどのような仕事か
――SDVでHondaを変革するための戦略や企画の中枢にいらっしゃる皆さんに、集まっていただきました。SDV事業開発統括部における戦略・事業企画はどのような仕事か、何を目指しているのか、そのあたりを語っていただきます。まずは、自己紹介からお願いします。

私は携帯電話などの通信系企業でソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタートしました。その経歴を活かしてHondaに入社して20年ほど、インターネットへの常時接続機能を備えたコネクテッドカーの開発に携わっています。途中、アメリカに6年間駐在して、そこでもコネクテッドの開発や運用をしていました。
私の部門は、2025年からデジタルプラットフォーム開発部という名前に変わりました。SDVのIn-Car※、Out-Car※でいえば、Out-Carに関わるすべてを我々が開発・運用しています。SDVに関わるソフトウェアをクラウド上で仮想化して開発できる環境の構築、SDVのデータ活用基盤を構築するのも私たちの仕事です。
これまでは、それらの開発と運用にフォーカスしていましたが、2025年度からは顧客価値の向上、あらたな事業機会の創出をさせるために、プラットフォームをもっと外に展開することも注力しています。
※In-Carとは 車内の機器やシステムを通じて、価値を提供する領域のこと。 ※Out-Carとは 外部の社会やネットワークとつながることで新たな価値を生み出す領域のこと。

私は2003年に新卒でHondaに入社しています。まずは栃木事業所に配属されて、カーナビやコックピットのHMI※の開発に従事していました。その後、東京に出てきて、最初は知能化領域――音声・画像認識に携わり、データアナリティクスや顧客UXといわれる部門の課長・部長を務め、今に至ります。
今のSDVプロダクト企画部には、これまで私がやってきた仕事がそれぞれ課として存在しています。それらが一つになって新たな価値を創出するデジタルラボ(Honda Software Studio Tokyo Shinagawa)の運営も、我々の仕事です。
そして、我々の部門のもう一つの大きな役割は、SDVを実現するデジタルプロダクトの企画開発ですね。私たちは、そのUX開発や各機能の企画をリードする立場にあります。顧客の価値がどこにあるかをデータから紐解く部隊もいて、それらが一体となり、優れたSDVプロダクトを世の中に提供する活動に注力しています。
※HMIとは Human Machine Interfaceの略で、人が機械やシステムを簡単に制御したり管理したりできる仕組みのこと。

私は2003年に中途採用でHondaに入りました。Honda入社後は、本社および海外現地法人にて、北米・欧州・中国でのパワープロダクツ事業における、地域サービス機能自立化や構築に従事し、うち10年間はイギリス・中国・タイに駐在していました。
24年4月からは四輪サービス技術開発部門を担当し、並行してソフトウェア提供・配信領域のリーダーとして、SDV事業開発における新組織立ち上げに参画。24年10月にOTA※や有線リプログラミングでソフトウェアを配信する機能を新組織に移管し、新部門を立ち上げました。
※OTAとは Over The Airの略で、無線通信を介してソフトウェアやファームウェアなどのアップデートを含む、クルマとのデータの送受信を行う技術のこと。

ソフトウェア配信においてOTAという手段がなかった時代は販売店でクルマに有線接続してソフトウェアを書き換えていましたが、ソフトウェアアップデートが将来の車両修理・サービスの主流になるという未来を描き、OTAシステムを開発し、手探りで運用を行ってきました。OTAはSDVでも重要なソフトウェア配信技術ですから、SDV事業開発統括部が立ちあがる段階で、その部隊を引き連れる形で新組織に機能移管したという流れです。
ソフトウェアの企画、開発から市場へのリリースにおける流れの中で、ソフトウェア配信は最終工程になりますが、単にボタンひとつ押すだけで配信できるものではない。クルマにおけるOTAは、スマホの配信と似ているようで同じものではありません。ソフトウェア自体の規模が大きいですし、バリエーションは国や車両によって異なる場合もあります。そのため、配信サーバー内のソフトウェアの組み合わせ構築プロセスの自動化や、地域を跨いだソフトウェア配信に向けた調整・連携プロセスの効率化しなければなりません。
こういった取り組みを推進するために、過去Hondaとして持っていなかった商品としてのソフトウェア商材のバリューチェーンを一から企画し、企画から提供まで一気通貫で実行できる効率的な体制及び運用プロセス、それに沿ったシステムの運用と必要な品質ゲート、及び責任者を配置する事で、品質担保をしながらソフトウェア配信を管理する体系を構築してきました。これは日本のOEMでも先駆的な取り組みだと思います。
加えて担当している部門ではソフトウェア配信と並行してSDV領域における企画から配信までの全体プロセスの構築や、統括部全体のリソース管理、お金の流れの見える化等、関連部門と連携して、組織価値の最大化に努めています。


私は1998年に新卒でHondaに入りました。入社後はエンジンの研究開発の部署で燃費や排出ガスのテストを担当していました。当時、若手を積極的に海外に派遣する制度があり、私も入社3年目でアメリカに赴任しました。その後はハイブリッド、EV化という流れで、ガソリンエンジン、ハイブリッド、FC(燃料電池)、EV、パワーユニットを一通り経験したのが自慢です。
2年前にSDV部門に戻り、現在は技術企画・デジタルプロダクトLPL(ラージプロダクトリーダー:開発責任者)の室長をやっています。この室のミッションは、一つはSDVの技術企画をまとめること。たとえばAD/ADAS、IVI、E&Eアーキテクチャなどさまざまな技術があるなかで、それをHondaの中長期戦略としてまとめるような仕事です。
もう一つはLPLですね。たとえば、シビックやN-BOXなど、Hondaにはいわゆるハードの機種ごとにLPL室が設けられています。個々の商品・機種のデザインも決められるし、どんな装備を実装するかもそこで決める。開発コストや売価にも決定権があります。Hondaでは役員クラスで構成される上層の部署なのですが、これからはそのデジタル版をしっかり作っていこうと、デジタルプロダクトLPL室を作りました。
機種LPLと対になるような形かつ顧客視点でそれぞれのハードに対応したプロダクトを考え、ソフトウェア企画をリードしていくんです。
――ソフトウェアを一つのデジタルプロダクトとして捉え、顧客視点でプロダクトの質を高めていく。その方法は、機種LPLとは同じなのでしょうか。

コアは同じだと思いますね。顧客のためにどのように商品を作っていくかが根本にある、といった点で同じではないでしょうか。たとえばパソコンを考えると、ハードは数年前のものだけれど、中のソフトウェアはどんどん新しくなって、使いやすくなってきていますよね。
そのような世界を私たちは、クルマのソフトウェアで実現していきたいんです。そのためのデジタルプロダクトを、森田さんのSDVプロダクト企画部がまずは考えて、PoCで本当に価値があるものかを実験し、商品化が決まれば、私の部門で具体的にデジタルプロダクトとして企画の詳細を詰めて、開発をリードします。
プロダクトが完成したら、板垣さんのSDVマネジメント部がOTAで世界中のクルマに配信・導入する。そのようにソフトウェアで車をどんどん進化させるわけです。ソフトウェアクラウドの運用については、野川さんのデジタルプラットフォーム開発部がしっかりサポートしてくれる、そういった連携があります。
SIerやサプライヤーで活躍してきた、入社1年半の副統括部長が目指すもの
――そして、そうした連携の全体を統括するのが、保永さんであると。

私はHondaに入社したのが2024年4月なので、まだHonda歴は1年半程度なんです。もともとは、SIerで通信キャリアの基盤構築など、BtoB事業を担当していました。その後、インターネットサービスプロバイダでBtoCの商品企画を行ったりスマホが出たばかりのころに、アプリ開発のプロジェクトマネジメントやサービス企画にも携わっていました。
そのころに、前職が事業売却されることになり、そのアライアンスの担当をした後に、別業界へ転職しました。これからはそれを使う側に移りたいと、Tier1※に入ります。いま、Hondaで野川さんの部門が手がけているコネクテッドカーの仕事を、私はサプライヤーの立場で関わっていたんですね。
※Tier1とは 完成車メーカーに直接部品を納品するメーカーのこと。

当時は「CASE」[「Connected(コネクテッド)」「Automated/Autonomous(自動運転)」「Shared & Service(シェアリング)」「Electrification(電動化)」]と呼ばれていた分野で、技術戦略を企画する仕事もしました。
これまでの自動車業界のレガシー領域とは全然異なり、ITが全面的に入ってくる。業界の融合、制度設計、サプライチェーンの見直し、契約内容の見直し、知的財産の考え方も変わらざるをえない。私はそういった改革におもしろみを見出していましたし、何らかの形で携わってきました。
その後は、なぜかもともと在籍していたSIerに戻って、CTO補佐を務めていたのですが、そのとき、Hondaの四竈さん(現 SDV事業開発統括部 統括部長)に会う機会がありました。そして一緒に飲んでいたらなぜかそれが選考試験で、気づいたらHondaにいた、という流れでした(笑)
現在はSDV事業開発統括部の副統括部長という立場で、HondaのSDV事業変革のための戦略や企画の立案と、そのオペレーションがメインのミッションです。

――「変革」には、人の採用や育成、あるいは予算管理なども含まれますか。

はい。女性の比率をもっと高める、日本だけではなくグローバルで採用を強化する、といったことも考えます。ここは人事部門と協働しています。
それと、HondaのSDV部門は、2024年の9月末までは「開発統括部」という名称でしたが、それが「事業開発統括部」と名前を変え、開発だけではなく、企画や事業、つまりビジネスを構想するメンバーがどっとジョインしました。戦略・企画・開発・運用・保守のプロセスを一気通貫で回そうという狙いです。そのプロセスをどのように作り上げるか、というところにまさに今ゼロからチャレンジしているところです。
こういった形に組織再編をすると、お金の流れも変わるんですね。Honda内での予算配分はもちろんですが、クルマを販売して利益を得る事業モデルだけではなく、サブスクのサービス展開も発生しうります。IT・ソフトウェア業界では当たり前のビジネスモデルですが、Hondaではこれまでほとんどやってきませんでした。そのための制度設計にも、一から関わっています。
実際に変革を始めてからの感想ですが、これらは結構大変なんですよね。これまでは開発費は開発部門だけでしか見れなかったんです。一方、事業開発・企画・運用などの他部門からも見られるようになると、会社全体でお金がどのように流れているかがわかるようになります。と同時に、それをしっかり管理しなければなりません。そのために、SDV部門としてお金の「見える化」にも取り組んでいます。
――統括部長の四竈さんは、保永さんのどこに惹かれて、副統括部長として採用を決めたのだと思いますか。

もともと大学では経済学と情報通信学という文理両方の修士号をもっていて、新入社員のころから営業企画でも技術の話がわかることを強みにしていました。調達部門にいたこともありますが、技術の話が理解できないと価格交渉もできませんから、そういったバックグラウンドは役に立ったと個人的には思います。
また、もともと社内外で人間関係を作るのが得意なんです。Hondaで採用してもらった理由としては、更地の状態から新たな事業を起こす変革のタイミングで、そういったタイプの人間が必要だったため、目をつけられたのだと思います。四竈さんに言わせると、私はブルドーザーのようなタイプらしいです(笑)
なぜ、SDV戦略・企画立案部門が赤坂に集結したのか
――これまでは、さまざまな企画の機能が、各拠点に分散していました。それを赤坂(Honda Innovation Tokyo Akasaka)に一気に集めたのはなぜでしょうか。

先ほど、荒井さんが説明したように、Hondaには機種ごとのLPLチームとその傘下に複数のプロジェクトリーダーがいます。それをデジタルプロダクトでも作ろうということで生まれたのが、デジタルプロダクトLPL室です。
これを上手く機能させるためには、やはり1つのオフィスに皆が集まったほうがいいだろう、という判断ですね。組織編成に合わせて、荒井さんはこのために栃木から引っ越して来てくれました。

SDVでは変革を「爆速」で進めるぞ、とよく言われますが、スピード感をもって意思決定するには、一つの拠点に集まるのが、やはり良い。オフィス集約の効果はすでに現れていると思います。

IT業界では、技術を目利きして投資し、どのように回収して提供価値を創出するかを検討する、一連の流れを一つの組織で一気通貫で行うのが一般的なんですよね。私がHondaに来た2024年10月時点では、組織がバラバラで、役割の分担が細分化されすぎている感じがあったと思います。
そこで、戦略企画の機能を置き直して、企画から開発に流れる仕組みをつくったり、開発費用の回収方法を検討して社内の経済を成り立たせたり……といったことをみんなで考える必要がありました。
こういった話を進めるには、さまざまなレイヤーの人材がコンパクトにまとまってワイガヤ※しながら話した方が早いんですよ。そんな体制が今のHondaには、すごくフィットしてると思いますね。
※ワイガヤとは? 「夢」や「仕事のあるべき姿」などについて、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論するHonda独自の文化。合意形成を図るための妥協・調整の場ではなく、新しい価値やコンセプトを創りだす場として、本気で本音で徹底的に意見をぶつけ合うもの。

プラットフォーム開発では、今までデジタルプロダクトの要件ごとにクラウドの機能を使ってもらっていたのですが、そうした単体の寄せ集めでは管理が難しい。実はもっと効率的にクラウドを構築したいけれど、それがなかなか難しいんです。
でも、開発と企画チームが一緒に話しながらお互いの考えをすりあわせられれば、先々のことも見通せるようになりますよね。今回の組織再編でお金の管理もまとめてできるようになったので、プラットフォーム開発もとても進めやすくなりました。

自分たちの主管部分だけでなく全体のお金の流れも見えるようになって、責任範囲が明確になりましたよね。全体像もつかみやすくなって、「じゃあ、次どうする?」ということも考えやすくなりましたね。組織再編と1オフィスへの集約は、表裏一体だと思います。
――実際、クルマでは企画から量産・販売・流通までの長いプロセスがあったわけですが、SDVではそのチェーンが非常に短くなりますね。それだけに仕事を細かく分業して、全体の意思がスムーズに流れないというのは、スピードの観点でリスクがありますよね。

そうですね。保永さんがこれまでに経験された通信やITの業界では当たり前の考え方を、SDV部門全体に広めるのも我々の役割だと思います。
もちろんSDVだけではなく、Hondaのほかの部門とも調整しながら、会社全体の文化を変えていく。最終的にはクルマを販売する現場、営業やサービスの現場も変わっていくはずです。

事業や開発だけで進めても限界があり、営業部門の巻き込みも必須です。プロセス、考え方、協働の仕方……。Hondaが思い描くSDVの未来のために、変革しなければならない上流工程はまだまだたくさんあります。そういった意味で、今回のメンバーは部門を越えてさまざまな仕事に携わっていますね。
先ほどのLPLもそうですが、今までになかったチームを作ったり、自ら顧客への提供価値を考えて実現方法を探ったりと、そういった流れの発信地が、このSDV戦略・事業企画部門なんです。これをいかにしてグローバルに展開するかが、今後私たちが立ち向かう課題ですね。
足元ばかり見ていても仕方ない。目指すゴールを常に共有
――皆さんのチームでは「一気通貫」と「爆速」が一種の合い言葉になっているわけですが、その変化になかなかついていけない部門もあるのではないでしょうか。

レガシーな事業モデルでは、クルマの機能においてソフトウェアのボリュームが小さく、ハードに携わる部門がマジョリティであり、権限も大きかったです。ただ、今はSDV開発がOEMの最重要事項です。そのため、投資ボリュームもSDV事業開発統括部が一番大きいですし、採用人数も多い。ビジネスの構造が大きく変わってきているんですね。
そういった意味で、時には対立が起きることもあります。変化のスピードも早いので足元ばかり見ていると、顔を上げたときに見える景色がガラッと変わってしまいます。もっと視野と視座を広げて、Hondaとして目指すゴールがどこにあるかを絶えず確認していかなければなりません。ゴールにたどり着く道は一つではなく、寄り道をしても同じゴールをともに目指そう、そのために役割分担しよう、という考え方にならなければ変革は進みません。

何十年にわたって積み上げてきたレガシーのなかで、細かいプロセス、ルーティン、規定があります。それをガラッと変えようとすると、どうしてもコンフリクトが起こります。
同じSDV事業開発統括部内でもそうですし、統括部外の車両開発、生産・品質・営業・サービスといった関連する周辺領域と、これまでにない概念で新たなプロセスを定めていく必要があります。そこの苦労はありますね。


私はもともとハードウェアのエンジニアでしたが、その間には、品質やサービスも経験しました。私も保永さんと同じくすぐに人と仲良くなれるタイプなので、これまでのキャリアでHondaのさまざまな部署につながりができました。
そういった意味で私は、SDVとほかの部門をつなぐ役割を果たさなければならないことを自覚しています。

機種LPL室は以前からありましたが、今後Hondaがソフトウェア・デファインドにシフトするなかで、SDV部門にもLPLを置くべきだ、という構想は数年前からありました。
この実現に着手したのが今年、2025年です。初代室長を誰に任せるか検討していたところ、荒井さんに白羽の矢が立ちました。現在のような変革期には、荒井さんのようにエンジン開発もやってきた人でハードとソフトウェアをつなげる、複数のドメインにまたがって仕事をしてきた人こそが適任です。
衝突はあれど、それを越えていける。Hondaならではの風土
――そういった接着剤がうまく機能するのは、やはりHondaならではの風土があるからでしょうか。

他社をいくつか経験した私から言わせてもらえば、Hondaの社風で良いところは人間力が高い人材が多いこと。
誰かのアイデアに対して「おもしろそうだから自分もやってみたい!」とポジティブに反応する人が多いのは、Hondaらしさだと思いますね。その分おしゃべり好きの社員が多いので、会議はやたら長いんですけどね(笑)

みんな喋るから会議が長くなる(笑) しかも、平気で横道にそれるし、「ワイガヤ文化」というのは、まさにそれですね。
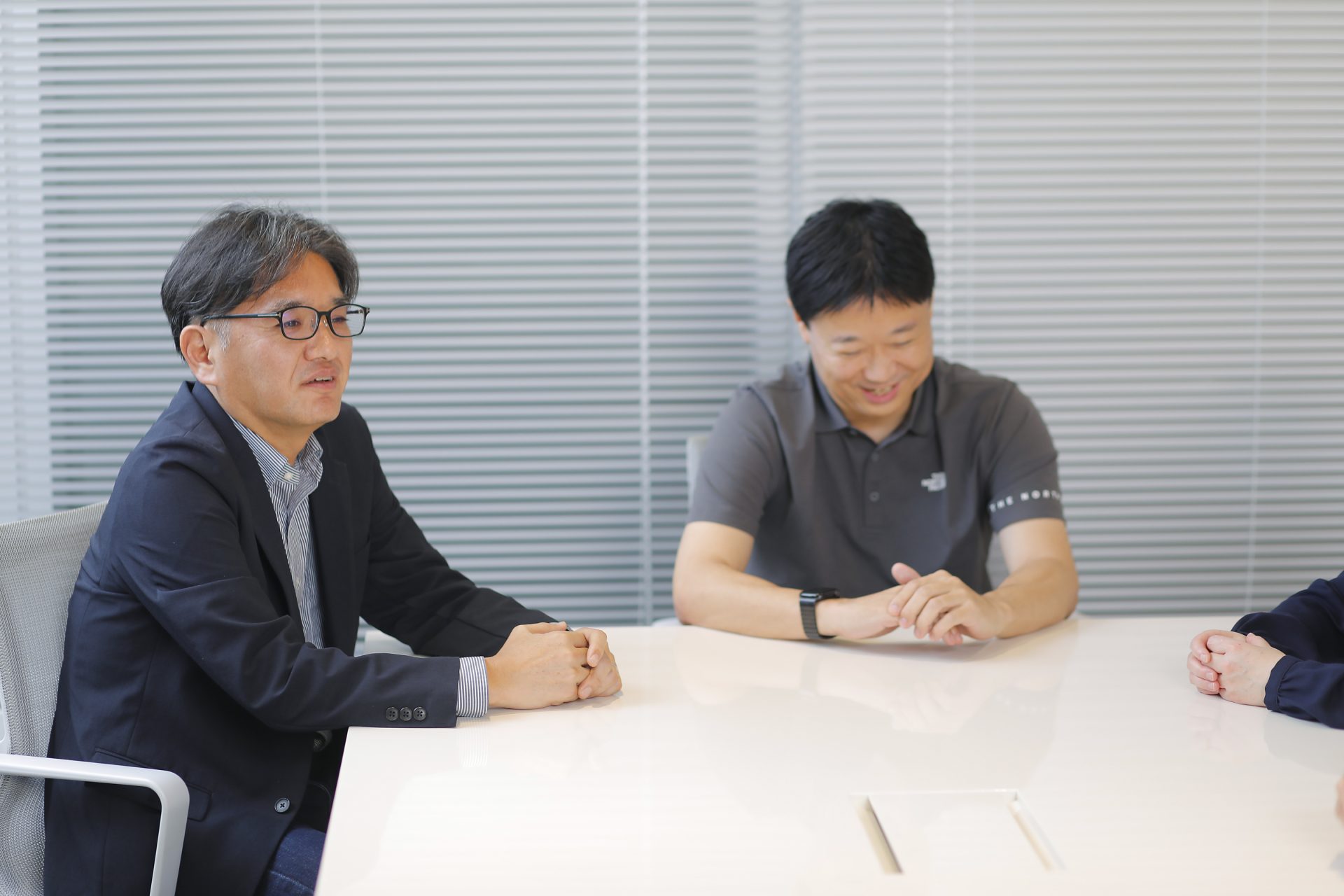
――一方で、これからのHondaがSDVの時代にグローバルに戦わなくてはならない相手は、クルマメーカーだけではありませんよね。競合には意志決定のスピードが相当速いところもあると思います。Hondaの今後のためにも、彼らのスピードと競わなければなりません。そのあたりは、どのようにお考えでしょうか。

「爆速」を掲げているくらいなので、Hondaの意思決定のスピードは早い方かな、と思います。もっと早くしたいですけどね。

やると決まれば早いですよね。ただプロセスをもっと標準化できたら、効率化できるところもあると思うので、そこはちょっと改善点だと思います。

これからは、クルマの部品や車体を作る業界以外のITやWeb業界もどんどん取引先になってきます。購買や開発部門でも、これまでとは毛色の違う人たちとコミュニケーションを取らなければなりません。
そうなると、これまでの自動車業界のやり方、ピラミット構造のようなやり方では通用しないこともあるでしょう。自分たちが変化しながら、異なる業界の人たちと会話ができて、文化が理解できるよう成長することが大切ではないでしょうか。私たち現場だけではなくて、本部長や役員も、変革に向けてチャレンジしたいと話しています。

別の業界と協働して、新たな価値を創造できたら良いですよね。

私は「協働相手に10年付き合えるベンダーさんをセレクトしましょう」と役員たちには言うんです。そのために、ITベンダーやクラウドベンダーのバックグラウンドや事業内容、実績などからインプットしています。
モビリティを軸にしたエコシステムをデザイン。SDV戦略・事業企画部門が求める人材
――SDV戦略・事業企画部門にも、これからは中途採用、新卒採用で新しい血を入れなければなりません。どのような人材にHondaへ来てほしいですか。

クラウド部門の人材は、クルマのことにかなり詳しい必要はないと思っているんです。クルマのスペシャリストは社内に山ほどいますから。それでも、まずはクルマをつくることがおもしろそうだなと思う人に来ていただきたいです。クルマとつながるクラウドを作ること=未来をつくること、ともいえるので、非常にワクワクする仕事だということをを知ってほしいですね。
テスラ社のイーロン・マスク氏も、次はフィジカルAI※だと言っています。彼らはロボットを作ってますが、私たちもクルマ以外にも、バイクや芝刈り機などのパワープロダクツ、航空、マリンなどのさまざまなモビリティを開発しているので、ポテンシャルとしては決して負けていないはずです。
例えば、AIやクラウド技術をクルマに持ち込めば、きっと勝てると思います。そういった意味で、これまでに培ってきた技術やスキルをクルマにもフィードバックできて、クラウドを軸にクルマの可能性を最大限拡張したい、と思ってくださるような人材がもっと増えると嬉しいですね。
また、クルマとつながるクラウドの活用をどんどん広げるべく、外部パートナーとともに、事業企画できる人材も必要です。モビリティを基点にエコシステム全体をデザインし、これまでにない事業を牽引したい、と考えている人材にはぜひHondaに来てほしいです。
※フィジカルAIとは AI(人工知能)の活用領域をデジタル空間からロボットなど物理世界に広げる概念のこと。

冒頭にもお話ししましたが、SDVプロダクト企画部には、さまざまな属性のエンジニアが在籍しています。
例えば、ソフトウェアをコーディングする方、データアナリスト、エンジニアを束ねるプロジェクトマネージャーなど、それらの人材はまだまだ採用したいです。そして、プロダクト開発の指針を作る方や、UX/UIエンジニアも必要です。ちょっと欲張りですかね(笑)
エンジニアは、荒井さんのLPL室でも必要なので、社内で引っ張りだこになります。逆にいうと、ジョブローテーションがしやすい側面もあるんですよね。LPL室と一緒に仕事をしていると、誰が直属の部門長で部下かわからなくなることがあります。でも、それが良い変化だと思うんですよね。
先ほどのワンフロアの話にもつながりますが、自分の役割だけで閉じずに、さまざまな部門の人とコミュニケーションをとりながら目標を達成する意欲のある方は、Hondaで活躍できると思います。
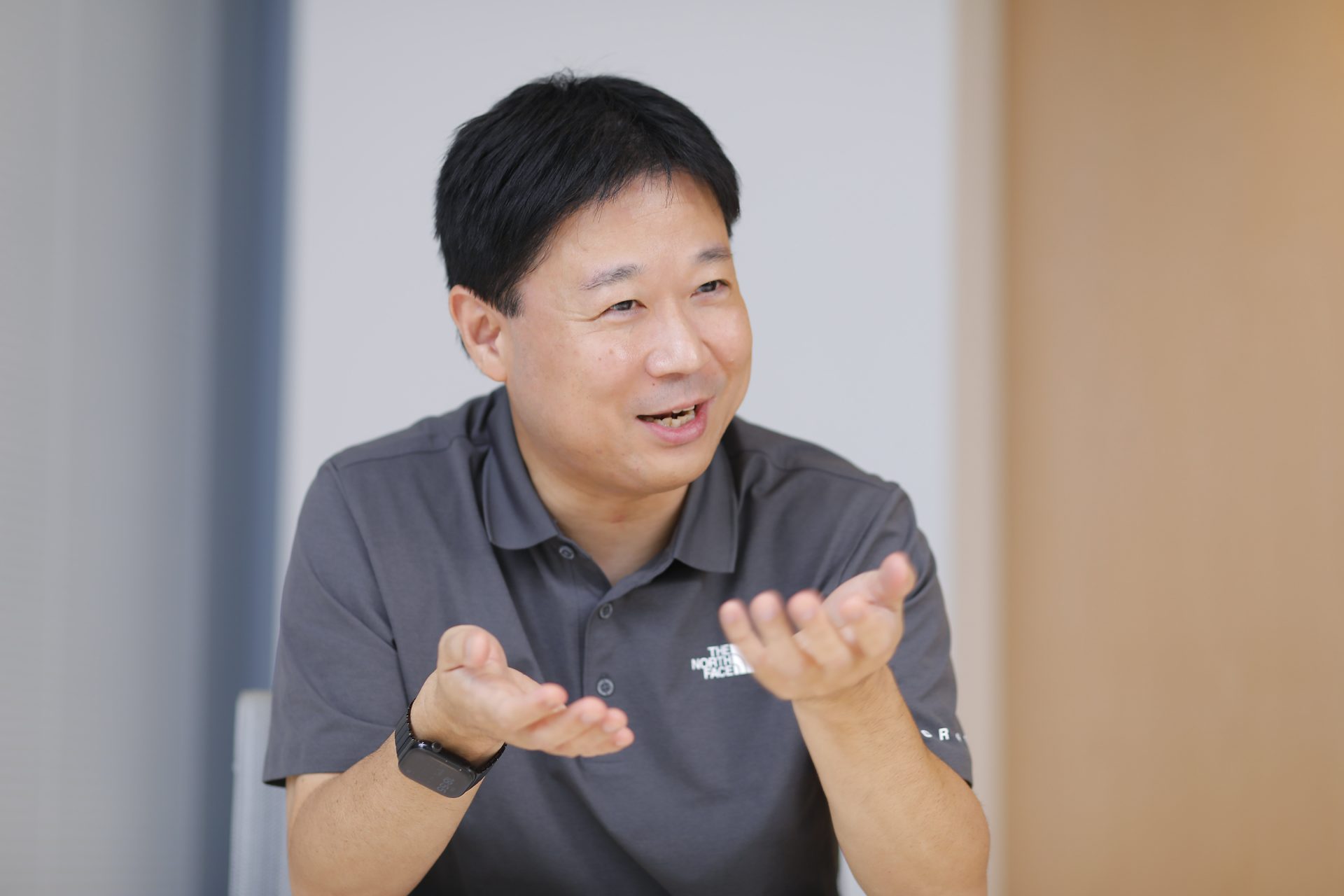

目標が同じであれば、部門問わず同じ方向に向かって走っていけるので、誰の指示でも関係ないですよね。

そもそも赤坂オフィスでは、ワンテーブルを囲って、私と部長陣が座っているんですよ。物理的にもいつでもコミュニケーションがとれる距離感なので、いつも何かしら会話しています。

メンバーも業務で関わりのある人同士で集まってお話ししながら仕事していますよね。
Honda SDV 企画セクションが求める人材
――板垣さんのSDVマネジメント部としては、どのような人材を採用したいですか。

何かひとつ強みを軸に持ちながら、私たちの事業に合うところに領域を広げたい人材がSDVマネジメント部には必要だと思います。強みを活かせる土壌はとても広いので、きっと活躍できるはずです。
SDVマネジメント部は母体がOTA配信をやっていた部隊がベースなので、Hondaのなかでも珍しいのですが、開発領域出身者とサービス領域出身者が同居しており、現場の困りごとを開発側に発信して改善する共創風土を大切にしています。
そもそも我々がカバーしているSDV領域におけるOTA配信やプロセス構築、リソース企画・管理の仕事は、あまり他社にありません。つまり、私の部で採用したい要件を100%満たす人材の絶対数が自動車業界に少ないということです。
自動車業界のOTAでは、ライフサイクルが長いため、面倒をみる時間が長いことや命に関わることなどの特性があります。そのため、品質をどのように担保するかにチャレンジしなければならず、その経験がある人材は、グローバルに見てもきわめて少ないのが現状です。
私たちはアメリカや中国のやり方を参考にしつつ、Honda流のやり方、ひいては日本流のやり方を模索していくしかありません。まずはプロセスを作って人材を育成したい、と思っています。

技術企画・デジタルプロダクトLPL室としては、クルマやIT好きな人材はもちろんですが、その前に、顧客、つまりは「人」が好きなことが必須要件ですね。「人」が好きな人こそ、良いプロダクトを作れる、というのが持論です。
それさえあれば、どのようなバックグラウンドがあろうと、活躍できると思いますね。実際、私の部門には、自動車業界出身の人以外に保険や広告、マーケティング界隈から来た人材もいます。多様なバックグラウンドを持つ人がそれぞれにチャレンジできる部署です。
野川さんの話にもありましたが、Hondaはさまざまなモビリティを持っている強みがあるので、そこで作られているエコシステムにはポテンシャルがあります。アプリ開発に取り組みたい人もいるはずですが、ちょっと違う軸を持つ新しいエコシステムのハブになりたい人は、ぜひ挑戦してほしいです。
――SDV部門をまとめる立場として、保永さんのお考えはいかがでしょうか。

自動車業界に限らず、いま日本の企業は人材獲得に苦戦していると思いますが、Hondaはかなり恵まれてる方だと思っています。転職経験がある私でも、こんなに若手社員が多い、平均年齢の低い会社に来るのは久しぶりなんです。
たぶん、それは夢の実現や生き生き感、自由な雰囲気で価値を作っていく、というHondaの社風に惹かれて人が集まっているのではないかと思います。別の会社や業界に長くいたからこそ、それを強く感じますね。
先ほど、森田さんからさまざまなバックグラウンドを持つ人材が活躍できる職場だ、という話が出ていましたが、得意のドメインが少なくとも2ドメイン以上あり、俯瞰して物事が考えられる、ジェネラリストタイプの人が向いているかもしれません。逆にいうと、自分の仕事しか見えない人にとってはなかなか難しいところもあると思います。
「バーチャルヘッドオフィス」という新しい試み
――社内においても人材育成は重要な事項だと思いますが、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

SDV事業開発統括部では、「バーチャルヘッドオフィス」という新しい施策を展開しています。30代後半から40代前半ぐらいまでのメンバーを15人ほど部長陣に選抜してもらい、本来の業務を兼務しながら、部長陣と同じ目線で仕事をしています。
本人が今までの経験からできること(CAN)と、これからやりたいと思っていること(WILL)を私がメンターとして確認し、それぞれの部長陣の育成方針や希望を聞いたうえで、経営課題にともに挑む取り組みです。これを部長より2つ3つ下のレイヤーのメンバーたちに体験してもらっています。
――一種の幹部候補生研修ですね。

他社さんにもそういった仕組みがありますが、Hondaにはこれまでなかったんですよ。部長職や役員たちがさばききれない仕事をともにOJTで担ってもらうことで、トップを目指す人材の意識改革を促し、視野や視座を広げ、これまで以上に広い人間関係を構築してもらいたい、という狙いがあります。そして、現在のバーチャルヘッドオフィスのメンバーの半数が、中途採用で入社した社員たちでした。
――新たな血が、さらに活躍できる仕組みづくり。SDVの時代を担う戦力作りが、始まっているわけですね。これからが楽しみです。
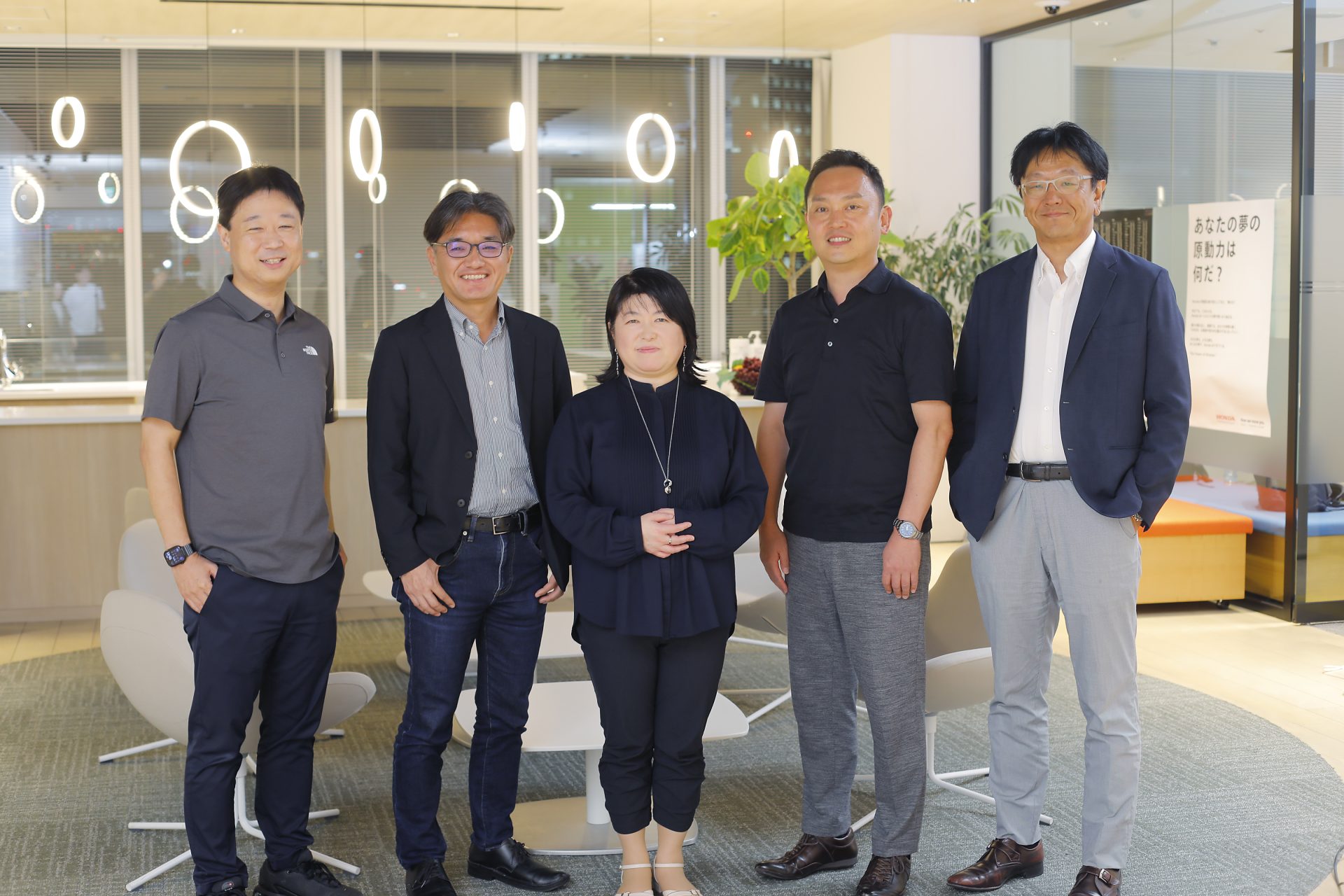
※記載内容は2025年9月時点のものです